| 仙台レコードライブラリー(直輸入・中古レコード専門店です) |
|
エセー 《観たい・言いたい・聴きたい》第30回 2025年12月30日 ヴェルディ《レクイエム》 ロンバルディアの詩人アレッサンドロ・マンゾーニはダンテと並べて評価される。代表作『いいなづけ』の決定訳は私が四十歳を越えた頃に出版され、十七世紀北部イタリアの社会描写と風刺を交えた波乱万丈の物語を一気に読んだ。思えば当時は世界の名作と呼ばれるものを看過できず、しかも敢えて長編に挑み、読了の達成感に浸るのが嬉しかった。『いいなづけ』は主役が庶民であるところに好感が持て、ヴィクトル・ユゴーの『レ・ミゼラブル』を上回る感動を得たことは覚えている。しかしながら、ヴェルディの話にこの物語を加えて深入りしたくても、私という老木の記憶の葉はすっかり朽ちて、もう一度この傑作を手に取る根気も失せてしまった。 還暦を迎えんとしていたヴェルディはマンゾーニの死の報に、《レクイエム》を捧げるべく霊感を得たと思われる。十九世紀のイタリアにとってもヴェルディにとっても、マンゾーニは杖とも柱とも頼む存在であり、彼が神に召されたことは、全イタリアを、そしてヴェルディの心を大いに揺るがせたに違いない。ここにオペラ作曲家ヴェルディは宗教曲の大作に挑むことになり、「オペラの衣装を纏った宗教曲」と呼ばれる大作《レクイエム》の作曲に取り掛かる。 その五年前にオペラ界の大御所ロッシーニが亡くなり、この時ヴェルディはこの偉大な作曲家のため、ミラノの音楽出版社リコルディに、これまで例のないレクイエムの創作を提案した。それは、ヴェルディを含む十三名の作曲家が各章の作曲を受け持つというユニークな企画だったが、結局は水泡に帰した。ヴェルディは最後の章『リベラ・メ』を書き終えており、再び訪れたレクイエムを書く機会にそれを流用した。 だが、前代未聞の激しさを持つ宗教曲が果たして尊敬するマンゾーニへの哀悼に相応しかったのだろうか。マンゾーニの死に、咆哮とも呼べる号泣が考えられようか。私はそうは思わない。マンゾーニの名は単に形だけのような気がする。レクイエムが愛する者の死を悼む音楽を意味するなら、ヴェルディの肩に重くのしかかっていた妻子の死以上のものは無かったはずだ。ヴェルディは二十五歳から二十七歳にかけて、娘と息子そして妻を相次いで亡くし悲しみのどん底に落とされた。《アイーダ》の初演を終えオペラ界の巨匠として君臨していた晩年のヴェルディの心を占めていたのは、一時も忘れたことの無い妻と子らであっただろう。悔やみ続けた心の吐露であれば、ありったけの嘆きをぶちまける音楽になっても当然だ。むしろ、これでも足りないとヴェルディは思ったかも知れない。それ故に、この作品を歌う時は、妻子を失った辛さを共有して歌って欲しい。 ヴェルディ没後百年に当たる二〇〇一年から翌年にかけて、私は幸運にも多くの《レクイエム》公演に巡り合った。その中で、ダニエル・バレンボイムとクラウディオ・アバード、そしてリッカルド・ムーティの演奏会について述べてみたい。それぞれに共通するのは、四人のソリストがいずれもオペラ界の第一線で活躍する歌手であったこと。これによって、少なくとも宗教作品のイメージが、それぞれの演奏からいっそう後退したことは事実である。 バレンボイムは耳を澄ましてやっと聞き取れる最弱音で開始し、「レクイエム」と、その静寂を破らないような若干強めの響きでベルリン・シュターツカペレの合唱が加わる。だが、この短いパッセージの中に、「レクイエム」と唱えながらも、最初から敬虔さを放棄してしまったような雰囲気が伝わってきて、この時点でバレンボイムの主張を受け入れられる者のみが感動を約束されているのではないだろうかという、不遜な思いにとらわれた。コンツェルトハウスの幾分固い響きもマイナスに作用したかもしれない。 ベルリン・フィルハーモニーでのアバードは、固唾を呑んで見守る中、祈るように静寂を保った「レクイエム」の主題が頭をもたげ、合唱の歌い出しでやっと幾分のふくらみが加えられ音量の豊かさに納得する。かつてエリック・エリクソンによって育成されたスウェーデン放送合唱団とエリクソン室内合唱団が訓練の行き届いた喉を聴かせる。オペラ合唱団を見慣れた目には彼らの若さが好ましく、生み出される声も当然澄み切っており爽やかである。だが、コーラスのこの特性が、「オペラ仕立て」の作品には負担となった。 ムーティはエイヴリー・フィッシャー・ホールでのニューヨーク・フィルハーモニックおよびウェストミンスター交響合唱団による演奏。弱めではあるがたっぷりした生命力溢れる表情で開始され、「主よ、永遠の安息を」と続いても、私には「生きなさい、生命の喜びを噛み締めなさい」と聴こえた。深読みすれば、開かれた天国の門に入らんとする喜びを表現したのかも知れないが、ムーティの生み出す響きはそんな敬虔なものでなく、もっと血の通ったものだった。 当時バレンボイムはシカゴ交響楽団への登場が多く、ゲオルク・ショルティ以来の強靭な金管楽器セクションを鳴らす技を身につけていた。「怒りの日」では、明らかにベルリンのオーケストラでの再現を試みたようで、そこに無理があり合奏のバランスは荒々しさの前に脆くも崩れた。ここでなお、宗教的な色合いを保っていたのは合唱団だった。なにしろ、合唱指揮者はヘルムート・リリンクに学んでいたエベルハルト・フリートリヒであり、バレンボイムの熱気から少し距離を置いていた。 「怒りの日」のテーマは何度も登場するが、合唱団のお行儀の良さによるものか、アバードの解釈なのか燃焼度が希薄だった。もっとも、至る所で美しい倍音を聴かせる類まれな合唱に多くの人が聞き惚れている中、アバードにせよそれを破壊したくない。だが、ただ一度劇的な音楽を迫力の上で最も高めたのは、「リベラ・メ」で再び登場する「怒りの日」の場面である。ここで一度だけ、アバードは両手を合わせて高く上げ、指揮棒と共に振り下ろした。勿論計算されたもので、曲のヤマをここに絞ってのことであろう。 ムーティの指揮で歌った合唱団の特徴は、五十代半ばを過ぎている者はいないように思われた。交響合唱団の名に恥じず、支えのしっかりした声による「怒りの日」は指揮者の巧みなコントロールの下に同じ形で統一された各声部が一糸乱れずリズムを刻む。ホールの音響にも救われて、オーケストラの振幅の大きな響きも一向に崩れなかった。 私は普段ステレオ録音初期にトゥリオ・セラフィンがローマ歌劇場のメンバーにより演奏したものを好んで聴いている。特に「ラクリモサ」でのフィオレンツァ・コッソットとボリス・クリストフが気に入って手が伸びるのだ。バレンボイムのステージで歌ったのはヴァーグナー歌手たちで、世界を沸かしていたワルトラウト・マイアーなどは、声量の豊かさも柔和な美しさも感じられなかった。これがホールに起因するものだったら心外だ。あるいは彼女は、オペラの場合は演技が伴って勝利するタイプなのかも知れない。 コッソットの声が耳に残っていた私にさえ、アバードの指揮で歌ったダニエラ・バルチェローナには引き込まれた。テンポや声量の微妙なコントロールこそもう一つだった「ラクリモサ」だが、感情移入の濃さが伝わってきて嬉しかった。声にまとまりもありこの日以来目を離せなくなった歌手である。 三十歳を越えて間もないバーバラ・フリットリがムーティとの共演の多いことは知っていたが、この晩ほど輝いて見えたのは初めてだった。それは華美を意味せず、至って奥ゆかしい印象だった。「ラクリモサ」はメゾ・ソプラノとバスに注目して聴く私だったが、思いがけないソプラノの歌唱に引き込まれた。全ての音域において艶やかで安定している歌唱に心奪われて聴き入った。彼女の凄さは歌っている時同様に、待機している間の緊張感にある。例え自分の出番でなくとも、彼女はすべてを音楽に投入しているのだ。ちなみに、三つのコンサートを通じて暗譜で歌ったソリストは彼女一人だけだった。 話題を移そう。ヴェルディ没後百年記念公演として、二〇〇一年一月に、ベルリンのフィルハーモニーではクラウディオ・アバードによる《レクイエム》が演奏された。注目を浴びたこの公演は映像化され多くの愛好家の観るところとなった。思いがけなく当日客席を占めることができた私は、その後映像でも楽しんだが、どうも幾つかの違いが気になっている。この公演が何日間続けられたものかは分らないが、実際聴いたものと映像は演奏日が異なるか、または、それらを編集したために私の聴いた演奏との差が生じたのだろう。このような比較は中々出来ないので、この機会に気が付いたことを述べてみよう。 放映されたのは一月二十七日、それはヴェルディの命日であり、私がベルリンで聴いたのはその前々日である。座席は最前列の右寄りで目立つところだった。だから、録音とは響きのバランスが大分異なっていただろう。先ずステージでは、期待したアラーニャの声は伸びず、私は不満足だったのだが、映像では完璧な声量で歌われていた。次に演奏終了と共にほとんど音楽と重なるほどに拍手が起きたにもかかわらず、映像ではそれが無かった。これは、放送と実演の違いなのだろう。また、私は何度も合唱団から立ち昇る倍音に感心したはずだが、マイクを通すとそれがすっかり消えていた。演奏会場からホテルに帰り着くや、二千四百字の感想文をまとめていたので、これらの比較ができたのだ。 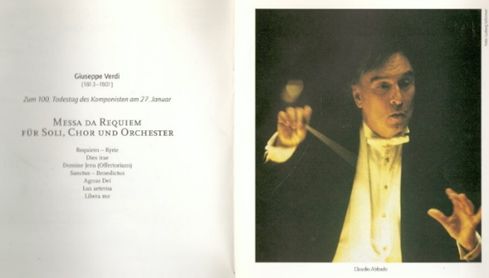 ヴェルディ没後百年記念公演《レクイエム》 のプログラム |
